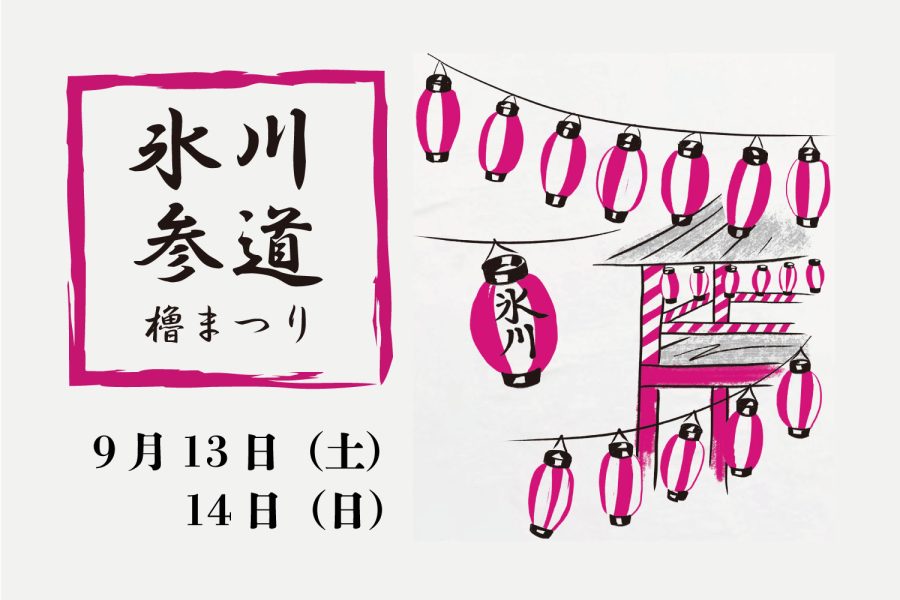住みたい街ランキングで上位になるなど、あこがれの地として注目を集める恵比寿。米ニューヨークや、仏パリなどで人気の店が、日本初の店舗を開くなど、最先端の情報が交差する印象があるが、裏道には八百屋、総菜店などの路面店が根を張り頑張っている。夏は各地区から神輿が出るなど“下町”の一面も持つ恵比寿の素顔を知るマダムたちに、街の歴史を聞く。

▼マダムEBISU Vol.1▼
新谷比佐(Hisa Shintani)さん
「gallery and shop 山小屋」店主
恵比寿駅西口から徒歩3分ほどの交差点にある「gallery and shop 山小屋」で店主を務める新谷比佐さんは、恵比寿に暮らして44年目になる。通りに面したギャラリーは、ガラス張り。宮崎駿監督のアニメ映画「魔女の宅急便」で、パン屋の店番をする主人公のキキのように、毎日行き交う人を見つめている。
「住み始めたころは、駅前はほとんど民家だった。豆腐屋とか個人商店が多かったのよ。『スタジオエビス』がある場所は乾物屋さんだったし。見える景色が変わったわ」。
サッポロビール工場跡地の再開発事業として、1994年に開業した複合施設「恵比寿ガーデンプレイス」、1997年に恵比寿駅に直結した商業施設「アトレ恵比寿」ができたころから街は急激に変化していく。
「それまでの恵比寿は、社宅も多くて。夕飯の買い物のために、魚や米屋に行く主婦が、エプロン姿で歩いていたりしたの。共同トイレのアパートもあって。寝間着姿の若者が定食屋に並んだり、若い人も多かった。いまは一定の収入がある人じゃないと暮らせない街になってしまったでしょう」と窮屈さを感じている。
人が集まる商業施設ができ、街を訪れる人も変わった。チェーン展開しているコーヒー店などが続々と誕生し、個人商店は経営難に陥り、閉店を余儀なくされた店も。地下が上昇したことで土地を売り、郊外に引っ越す知り合いも増えた。
「この20年で急に変化したから、『さみしさ』よりも、『暮らしにくさ』の方が先にあって。良い街じゃなくなってしまった。『渋谷に埋もれた街』と呼ばれていた、むかしが懐かしい」
周囲が騒がしくなっても、愛娘2人を育て上げた恵比寿を離れないのは、下町の名残りに愛着を感じているからだ。
「田舎から野菜が送られてきたから食べて」とかできたおかずを交換したり。長く恵比寿を見ている住人同士のつきあいは変わらない。「なくなったのは、道を聞かれることくらい。スマートフォンができたから」と笑った。
外の世界は目まぐるしいが、柔らかい光りが差し込むギャラリー内は、時間が止まったよう。木のぬくもりを感じられる外観や扉は、比佐さんを慕う人の手作りだ。衣類や器、アート作品などを展示したいクリエイターと、訪れた人をつないでいる。期間限定の出合いは、奇跡の連続だ。
1秒、1秒。恵比寿の街で、自分の時間を刻んでいる比佐さん。
「わたしは動かないから、街を出て行った人が『何十年ぶりかに来たよ』と店に寄ってくれることもある」
優しい笑顔は、恵比寿の守り神のようだ。
取材中、時折ちょこんと頭を下げて行く人の姿があった。気付くと手を振り「あれは、ひいらぎ(鯛焼き店)の横の店のレストランのマスターよ」とうれしそうに教えてくれた。
言葉を交わしたことがなくても、いつも通る人の顔を覚えている。「きょうは腰を押さえて痛そうね」、「あら、久々に見たらずいぶん歳を取ったわね。なんて勝手に思ったりもするの。お互い様だけどね」。
「着地点が見えないことはしないの。背伸びをするとけがをするから、無理はしない。けれどここ一番はね、精いっぱい頑張るのよ」
胸に響く言葉には、栄養がたくさん詰まっていた。
■大切にしていること
多くを持たずシンプルに生きること。食事も粗食が一番。でも、出汁を丁寧に取ったり、手をかけたものを、味わっていただくことの方がずっとぜいたくで、心と体を労わることだと気がつきました。 ファッションも、いまの人はものは溢れているけれど、おしゃれな人は少ないと感じる。ポケットを付け替えたり、刺繍をしたり。心地よさを加えると、自分らしさが引き立つと感じます。
■恵比寿は何色?
渋谷に埋もれた街と呼ばれていた頃はグレー。いまはまだら色。見る人、角度によって見え方が変わるから。
文:西村綾乃
イラスト:ウチヤマカオリ